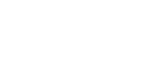今回はインプラントの構造や役割、種類について解説します。インプラント治療が気になっているけれど、よくわからなくて不安だという方は、ぜひ参考にしてみてください。
インプラントの構造と役割
メーカーにもよりますが、一般的にインプラントは、上部構造、アバットメント、インプラント体の3つの構造で成り立っています。それぞれの構造の役割について解説します。
上部構造(人工歯)
上部構造はインプラントの最上部に設置される、セラミックなどを素材としたパーツのことです。実際にものを咀嚼する役割を持ちます。外から見える部分であるため、審美性に優れたセラミックが使用されるケースが多いです。
アバットメント
アバットメントは、上部構造とインプラント体を接続する金属の小さなパーツのことです。インプラント体の上にアバットメントを連結し、その上に人工の歯を被せてインプラントが完成します。
アバットメントの役割は高さ調節です。歯肉の厚さやインプラントの埋め込む角度などによって最適なものが選ばれます。噛み合わせが悪くならないように、形にも少しずつ違いがあります。
インプラント体
インプラント体は、インプラントの土台になる部分です。材料は主にチタンが使用されます。チタンは生体親和性が高く、アレルギー反応を起こしにくいという特徴があります。インプラント体の大きさは様々で、使用する部分によって使い分けられています。
一般的にインプラント体はネジ状をしていて、専用のドライバーであごの骨に埋め込みます。ネジの形をとることでインプラント体とあごの骨が接触する面積が広くなり、骨と結合しやすくなります。
インプラントの種類
日本では20種類以上のインプラントが販売されていますが、大きく分けて、ワンピースタイプとツーピースタイプの2つがあります。機能的には大きな差はありませんが、用途や治療回数によって採用する種類が異なります。
ワンピースタイプ
ワンピースタイプは、アバットメントとインプラント体が一体になっているインプラントです。手術の回数が1回で済むため、身体にかかる負担を抑えられるのがメリットです。
しかし、ワンピースタイプを使用できるのは、あごの骨の厚みが十分にあると判断された方だけです。
また、アバットメントに問題が生じた際は、インプラント体ごと除去しなければならない点にも注意が必要です。
ツーピースタイプ
インプラント治療で主流なのが、アバットメントとインプラント体が別のパーツになっているツーピースタイプです。ワンピースタイプと違い、あごの骨の厚みが十分でなくても治療がしやすいという特徴があります。
原則として、2回の手術が必要ですが、万が一、強い衝撃を受け、アバットメントが折れてしまっても、インプラント体へのダメージが避けられるような構造になっています。
参照:https://www.takada418.jp/column/structure
構造を理解したうえでインプラント治療を
インプラントの構造や役割について解説してきました。インプラントは、主に上部構造、アバットメント、インプラント体の3つに分かれていて、天然の歯と同じように咀嚼できるよう、それぞれに役割があります。
インプラントの種類は大きく分けて、ワンピースタイプとツーピースタイプがあり、現在はツーピースタイプが多く使われています。
一言でインプラント治療といっても、様々なバリエーションがあります。それぞれに合わせた治療を行うためにも、構造をよく知ったうえで歯科医師に相談しましょう。